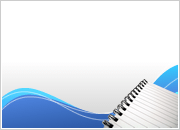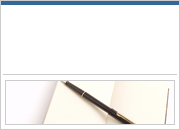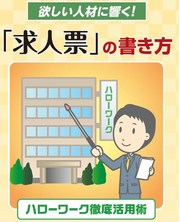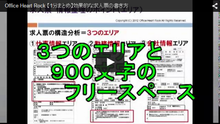- ホーム
- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS
- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方
- 【8/28讀賣新聞17面】変わる主婦パート②”広がる正社員への道”から人事戦略を検証しました。
【8/28讀賣新聞17面】変わる主婦パート②”広がる正社員への道”から人事戦略を検証しました。
2014/08/29”広がる正社員への道”
”「ありのママで」即戦力”
「変わる主婦パート①」に続く
8/28讀賣新聞17面、特集記事
「変わる主婦パート②」の
ヘッドラインです。
・ パートを活用する約1450社のうち、
正社員登用制度を持つ企業は、46.8%
04年調査時の1.5倍
・ 働く側にもメリットは大きい。
正社員になれば、無期雇用となり、
育児休暇などが取りやすくなる。
・ フルタイムや転勤を前提にした
正社員への転換は育児中の主婦には、
ハードルが高い。そこで最近、広がって
いるのが、「限定正社員」だ。
※以上、当該記事より引用。
そして、この記事で紹介されているのが、
”「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書”
〜「多様な正社員」の円滑な導入・運用のための提言〜
という位置づけで昨年9月から14回、
「多様な正社員」の雇用管理をめぐる課題が検討され、
7月30日 厚生労働省から報告書が公表されました。
今般、WEB上に公開されている、
この報告書を入手しました。
今回は、限定正社員を含む「多様な正社員」
をめぐるデータ・メリット・課題をご紹介するとともに、
人事戦略を検証しました。
※以下のデータは、厚生労働省、
”「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書”
公開資料から引用します。
1.正規雇用と非正規雇用の推移

1985年からの推移です。
現在は、役員を除く雇用者全体の36.7%という状況です。
2.「限定正社員」のバリエーション
この報告書で提言されている「限定正社員」。
「多様な正社員の効果的な活用が期待できるケース」として、
以下の3つのバリエーションが提言されています。

3.導入状況と目的
(1)「多様な正社員」、導入状況【全体】

アンケート対象の約5割の企業が
「多様な正社員」の雇用区分を導入との状況です。
(2)「多様な正社員」、導入状況【業種別】

業種別区分でみると、
勤務地限定正社員については、
・不動産業、物品賃貸業(42.9%)
・金融・保険業(39.0%)
・建設業(23.5%)
職種限定正社員については、
・医療・福祉業(52.9%)
・教育・学習支援業(32.9%)
・運輸・郵便業(33.3%)
という集計結果でした。
(3)「多様な正社員」、導入する「目的」

このように
・人材確保・定着の必要性
・正社員の働き方の見直しの必要性
の目的が多く挙げられています。
4.「多様な正社員」、賃金水準の差

「80〜90未満」との回答が約25%と最も多い結果でした。
5.「多様な正社員」、解雇
勤務地・職種の「限定正社員」が
事業所閉鎖(勤務地)・職務の廃止(職種)となった場合等の
解雇について以下の提言がなされています。

6.「多様な正社員」、均等処遇
「正社員」と「多様な正社員」の均等処遇に関する提言です。

7.人事戦略の検証
以上の提言。
私が実際に、この制度に関する、
人事コンサル現場の経験も踏まえ、
私見ながら、
「限定正社員」に関する人事戦略には、
以下の3つのポイントがあるかと考えます。
(1)「正社員」⇔「多様な正社員」相互の転換ルート
そもそも論として、報告書での
「導入の目的」での統計データにもあるように、
・人材確保・定着の必要性
・正社員の働き方の見直しの必要性
であれば、従業員の状況として、フルタイム勤務が可能な
時期がくれば、正社員への転換。
逆の時期であれば、一時的にでも
「多様な正社員」での継続勤務という相互の転換ルートを
設けておくことが、会社にとって、貴重な人材を維持・定着に
有効であると考えます。
この報告書においても、以下の提言がなされています。

(2)職務評価基準の設定
「多様な正社員」に関する就業規則への記載は、
周知・ルール化からは当然のこととなります。
寧ろ、大事なことは、
パート→多様な正社員⇔正社員
とキャリアパスを制度として設ける場合、
「希望者全員」とは行かない会社事情が多いかと考えます。
任用・登用の「公平性・納得性」の担保のためにも、
客観的な任用・登用の「職務評価基準」の設定が重要です。
報告書においても、このような提言がありました。

(3)給与水準の設定
これについては、
「多様な正社員」給与水準の設計・設定に
「納得性」・「合理性」が重要になります。
ひとつの方策として、
「要素別点数法」による職務評価を根拠とする
手法があります。

※厚生労働省 キャリアアップ助成金リーフレットより引用。
この手法。
私も、厚生労働省の講習研修会でお聴きしましたが、
”ポイント”による数値化をベースとしており、
給与金額という”数値”との親和性の高い評価手法と
考えています。
最後までお読み頂き有難うございました。
では、また。
※本コラムの内容は、各所取材の上、入手した情報を基に、
記事として掲載させて頂いております。
・新定番!な求人票の書き方のノウハウ・求人戦略情報 満載! コラム好評連載中!
【応募率94.8%! のノウハウ 】: 新定番!な求人票の書き方
▽
http://www.heartrock-noma.com/contentscate_127_1.html
・ソリューション・メニュー
【新定番な求人ノウハウ】94.8%の応募率! 求人原稿コンサルティング
▽
http://www.heartrock-noma.com/contents_327.html
【2時間でわかる!欲しい人材に会社をPR!】”新定番!”な求人票の創り方セミナー
▽
http://www.heartrock-noma.com/contents_297.html
※ご相談・お問い合わせは、下の「ご相談・お問い合わせフォーム」からお願い致します。
【応募率94.8%! のノウハウ 】: 新定番!な求人票の書き方
▽
http://www.heartrock-noma.com/contentscate_127_1.html
・ソリューション・メニュー
【新定番な求人ノウハウ】94.8%の応募率! 求人原稿コンサルティング
▽
http://www.heartrock-noma.com/contents_327.html
【2時間でわかる!欲しい人材に会社をPR!】”新定番!”な求人票の創り方セミナー
▽
http://www.heartrock-noma.com/contents_297.html
※ご相談・お問い合わせは、下の「ご相談・お問い合わせフォーム」からお願い致します。
労務関連ニュース、毎月メルマガでお届けします!