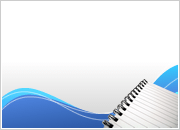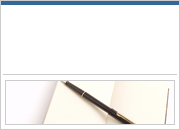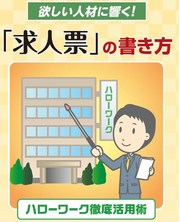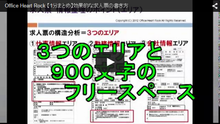- ホーム
- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS
- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方
- 令和4年版労働経済白書で考察 "転職先を選んだ理由"と求人票の書き方 [求人票の書き方 #14-2022]
令和4年版労働経済白書で考察 "転職先を選んだ理由"と求人票の書き方
[求人票の書き方 #14-2022]
2022/09/23
***求める人材像の考え方/求人票の書き方***
「令和4年版 労働経済の分析」(労働経済白書)
労働経済白書とは、一般経済や雇用、労働時間などの
現状や課題について、統計データを活用し分析する報告書
2022年9月6日 厚生労働省は
73回目となる白書を公開しました。
公開された白書には、
求人募集・採用活動の参考となる
データ・分析資料も掲載されています。
今回のコラムは、
「転職者が勤め先を選んだ理由」にフォーカス
調査結果の概要をご紹介し、
求人票の書き方を考察します。
※以下の資料は、厚生労働省ホームページに
公開されている資料より引用します。
[令和4年版労働経済白書より] 転職者が「現在の勤め先を選んだ理由」
「令和4年版労働経済白書」
第Ⅱ部 第2章 第3節 のテーマは
「転職者の実態」
男女別・年齢階級別に
「現在の勤め先(=転職先)を選んだ理由」の
調査・集計結果が報告されています。
白書によれば、
男性と女性との相対比較・傾向について
・男性は「自分の技能・能力が活かせるから」を理由とする
"能力発揮"を目的に転職先を選ぶ傾向が高い
cf.
35~44歳 男性:24.3% 女性:14.4%
45~54歳 男性:23.1% 女性:15.5%
・女性は「労働条件(賃金以外)がよいから」・
「転勤が少ない、通勤が便利だから」を理由とする
"働き方や労働環境を意識"した理由で転職先を選ぶ傾向が高い
「労働条件(賃金以外)がよいから」
cf.
25~34歳 男性:15.8% 女性:21.9%
35~44歳 男性:12.5% 女性:19.1%
「転勤が少ない、通勤が便利だから」
cf.
25~34歳 男性: 8.1% 女性:11.5%
45~54歳 男性: 7.4% 女性:20.7%
年齢階級別の傾向については
・「55~64歳」の年齢階級においては
男性・女性とも「自分の技能・能力が活かせるから」という
"自身のキャリアをいかせるどうか"で転職先を選ぶ者の割合が比較的高い
cf.
25~34歳 男性:13.9% 女性:10.2%
35~44歳 男性:24.3% 女性:14.4%
45~54歳 男性:23.1% 女性:15.5%
55~64歳 男性:33.8% 女性:28.2%
・54歳以下の年齢層では
「仕事の内容・職種に満足がいくから」という
"仕事の満足度"を理由に転職先を選ぶ者の割合が比較的高い
cf.
25~34歳 男性:21.0% 女性:23.7%
35~44歳 男性:15.5% 女性:18.9%
45~54歳 男性:22.0% 女性:15.5%
55~64歳 男性:13.2% 女性:14.4%

※青のヒストグラム:男性 橙のヒストグラム:女性
図表出典:令和4年版 労働経済の分析 第Ⅱ部 第2章 第3節 転職者の実態
以上の分析結果が報告されています
※白書詳細は、下記
【出典・引用】URLからご確認ください。
欲しい人材に響く! 求人票の書き方 ( 求める人材像の考え方/求人票の書き方 )
労働経済白書で報告された
「現在の勤め先を選んだ理由」
ご紹介した男女別・年齢階級別の特徴・傾向は、
「仕事選び・転職先を決める理由は
年齢・性別さまざまな要素で異なる」
こと
を示唆しています。
これを求人レベルに置き換えると
「求人票で興味・関心ありそうな情報/
重視しそうな情報/フック・ヒットしそうな
情報は人材像で異なる」
と言えます。
さて、
求人・採用戦略においてよくよく語られる
「求める人材像の明確化」というテーマ
ともすれば、
新卒採用でありがちな
・コミュニケーション能力の高い人
・自ら考え主体的に行動できる人
・高い意欲で新しいことに挑戦できる人
などの標語に代表される
性格/行動/意欲などの"ポテンシャル"な要素
中途採用でありがちな
・〇〇ができる人/経験のある人
・〇〇経験△年以上
・〇〇資格を持っている人
などの標語に代表される"スペック"の要素
に目が行きがちです。
しかし、
求人・採用活動の本質は
後々の定着も視野に入れて考えると
「ポテンシャルやスペックが高い人を採用すること」ではなく
「自社の仕事ができる人、社風・職場にマッチした人」を
採用面接で見極めて採用することにあるはずです。
2012年(平成24年)以来、10年にわたって
弊所が本連載コラムや商工会議所などでの
「求人票の書き方セミナー」等の機会に
繰り返しお伝えしていることは
「求人とは、集客。」
「求人票も、広告。」
という視点・考え方
広告をつくるときの最初のステップは
「訴求するターゲット」の明確化・設定
求人では「求める人材像」の設定に相当するところですが、
「誰に売り込みたいか?」を明確することが
広告のゴールではありません。
寧ろ、大切なのはここからのプロセス
明確化したターゲットに、
自社の広告に反応してもらわなければ
広告を出す意味がありません。
・その人は、どんな働き方に関心があるのか
・その人は、どんな職場環境に興味があるのか
・その人は、仕事選びに何を重視しているのか
自社の想定するターゲットが
「働き方や労働環境を意識」するタイプであれば、その情報を。
「仕事の内容・職種を重視」するタイプであれば、その情報を。
自社が求める人材像の価値観・志向などをイメージして
どんな求人情報を、どんな言葉・表現で伝えるかが
求人票の書き方の大切なポイントです。
求人広告である以上、
広告の読み手が存在します。
巷の「求人票のひな型/サンプル」でもみかけますが
会社の都合/一方的に言いたいことを羅列して
文字で埋める求人票が「詳しい求人票」ではありません
「詳しい求人票」とは、読み手である求職者の印象。
自分が仕事選びで欲しい情報/知りたい情報が、
わかりやすく網羅された求人票のことです。
いくら「うちの求人票は情報量が多い」と自負していても
「欲しい人材が、一瞥してスルー / 一読してスルー」するような
独り善がりな内容では、そこから
応募に繋がることは期待薄です。
大切なことは
「欲しい人材像は?」ではなく
「だれに・なにを・どう伝えるか?」
自社が求める人材に向けて、
伝えるべき情報を取捨選択して
伝わる表現・文章を吟味して的確に発信する
そのプロセスは、広告のそれと
同じであろうことは想像に難くありません。
求人票も書き方・伝え方次第で
その印象はガラリと変わります。
みなさんは、仕事を探しているみなさんに
今、求人票で「なにを・どう」伝えたいですか?
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
【出典・引用・参考】
厚生労働省 報道発表 2022.09.06
「令和4年版 労働経済の分析」を公表します
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27381.html
令和4年版 労働経済の分析
▽
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/21/21-1.html
※本連載コラムは、各省庁ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。