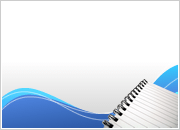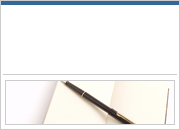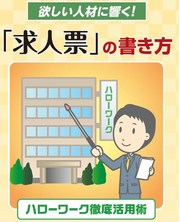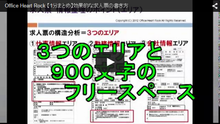- ホーム
- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS
- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方
- 2020年版ものづくり白書にみる製造業の求人戦略(経営課題と人材) [求人票の書き方 #30-2020]
2020年版ものづくり白書にみる製造業の求人戦略(経営課題と人材)
[求人票の書き方 #30-2020]
2020/06/09
【連載コラム:求人票の書き方 #30-2020】
経済産業省/厚生労働省/
文部科学省 3省共同執筆による
ものづくり基盤技術の振興に関して
講じた施策に関する報告書です。
20回目となる今回の
メインテーマは「企業変革力」
「ものづくり人材の確保と育成」
企業変革力を高めるために必要な
"人材強化"についてさまざまな
角度から分析・レポートしています。
本連載コラムでは、
ものづくり白書を特集。
・ものづくり現場の経営課題と人材
をピックアップ
人材採用・確保に関するデータから
製造業の求人戦略/求人票の書き方を
読み解きます。
各ホームページ公開資料から引用します。
ものづくり現場の経営課題と人材(「2020年版ものづくり白書」第2章より)
"大企業と中小企業"に区分
傾向・特徴をレポートしています。
・価格競争の激化:43.0%
・人手不足:41.9%
・人材育成・能力開発が進まない:40.9%
・原材料費や経費の増大:36.8%
の順に
中小企業では
・人材育成・能力開発が進まない:42.8%
・人手不足:42.2%
・原材料費や経費の増大:32.1%
・価格競争の激化:29.1%
の順に
人材確保・育成に関する課題認識が
より鮮明な結果となっています。
また、同じ人材関連項目のうち、
「後継者不足」については
大企業:22.7% に対し
後継人材確保の課題認識についても
特徴がみられる結果となっています。
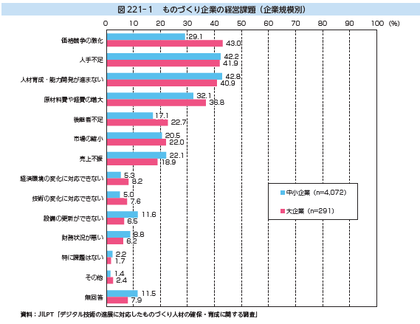
「令和元年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)を取りまとめました
▽
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200529001/20200529001.html
2020年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)
▽
https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2020/honbun_pdf/index.html
独立行政法人 労働政策研究・研修機構 2020.05.27
「デジタル技術の進展に対応したものづくり人材の確保・育成に関する調査」結果
▽
https://www.jil.go.jp/press/documents/20200527.pdf
欲しい人材に響く! 求人票の書き方( 人手不足と人材育成 求人募集のバランス感覚 )
「人手不足と人材育成」
2つの経営課題
ものづくり企業各社の
事業内容・技術力・人員構成など
諸々の事情によって、
そのバランス・プライオリティが
異なるであろうことは想像に難くありませんが
「採用と育成」は人材確保の車の両輪
そして、人材採用の入口である
求人募集のフェーズでは
自社の採用方針・欲しい人材像に
適う求職者からの応募を促すことは、
入社後の早期離職の回避・定着率の向上の
観点からも重要な戦略です。
「欲しい人材像の明確化」
求人戦略でよく語られていますが
明確にしておくことは
”〇〇できる人”といった
能力・スキル要件だけではありません。
採用方針に強く関係する要素は、
・短期スパンの貢献を期待する即戦力人材を採用するのか
・長期スパンの貢献を期待する育成人材を採用するのか
といった採用のベクトル
ここが曖昧なままだと
・入社後の育成で伸ばすスキル
・入社時に欲しい経験・スキル
の切り分けが不明瞭のままに
募集⇒面接⇒採用⇒育成の
サイクルを回すことになり
ミスマッチ⇒早期離職⇒再募集の
悪循環に陥ることにもなりかねません。
そして、応募者を集める
求人票・求人情報のコンテンツも
自社がどんな人材を求めているかで
発信する情報が変わってきます。
「即戦力人材を採用する」のであれば、
・どんな役割・成果が求められているのか?
・どんな職場の環境で働くことになるのか?
・どんな処遇/労働条件が用意されているか?
といった事柄・情報が、
その立場の読み手の興味・関心事でしょうし
「育成人材を採用する」のであれば、
・入社後はどんなカリキュラムで育成するのか?
・社内の育成体制は/Off-Jt・OJTなどの体系は?
・5年/10年スパンでみた社内のキャリアプランは?
といった事柄・情報が、
その立場の読み手の興味・関心事であろうことは
想像に難くありません。
ただただ、
自社のアピールポイントを
事柄の関連性も脈絡もなく、
上から下に羅列することが
「詳しく書かれた求人票」ではありません。
「詳しい・詳しくない」は、
あくまで読み手の主観
"自分にとって欲しい情報"が
そこに網羅されているかどうかです。
2012年(平成24年)以来、
本連載コラム・求人票セミナーなどで
お伝えしていますが、
「求人とは、集客。」
「求人票も、広告。」です。
求人票・求人情報は、
"誰でもいいから"ではなく
「読んでほしい・応募してほしい」
人材像(読み手)が存在します。
その読み手は、
自社が仮定する「欲しい人材」
自社求人が狙うターゲットです
・ターゲットによって、見せるものを変える
・ターゲットによって、伝える内容を変える
・ターゲットによって、文体・表現を変える
は、その本質においては広告コピーのそれと一緒
「●●で〇〇なお仕事です」
「▲▲さん活躍中!△△な職場です」
「■■は□□なので安心です」
いかにも"あるある"なコピーが響くどうかも、
読み手の感性次第
伝える言葉も、読み手の興味・関心も、
生きものです。
「こう書けば、必ず応募者が集まる」
そんな絶対法則的な書き方・文章表現など
存在しないことは想像に難くありません。
求人票も書き方次第
求人情報も伝え方次第
「見慣れた表現」・「ありがちな言葉」ではない
"自分の・自社の言葉"で紡ぐ
他社とは違う「自社で働く魅力」
自由な発想とオリジナリティあふれる言葉で
求人情報の読み手に伝えおきたいところです。
みなさんは、まだ見ぬ"欲しい人材"に
なにを・どんな言葉で・どうやって伝えますか?
弊社では、
ハローワーク求人票、求人・事業所PRシートをはじめ
採用ページ・各種媒体のリライトなどのご相談も対応しております。
よい採用の実現に、弊社のノウハウをご活用頂ければと存じます。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸いです。
※本連載コラムは、各所ホームページ公開情報等
取材した内容を基に、記事として掲載しています。