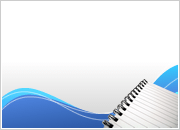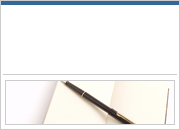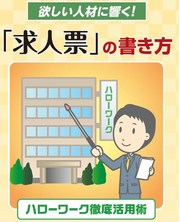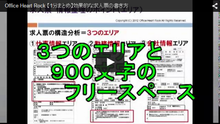- ホーム
- [求人ジャーナリストの連載コラム] Heart Rock Frontline NEWS
- 【連載コラム:求人票の書き方 】:欲しい人材に響く! 求職者から「選ばれる」求人票の書き方
- 【4/17リリース!】「2014年度 新入社員『会社や社会に対する意識調査』」から就活生への求人戦略を検証しました。
【4/17リリース!】「2014年度 新入社員『会社や社会に対する意識調査』」から就活生への求人戦略を検証しました。
2014/04/25
日本能率協会
2014年04月17日ニュースリリース
新入社員「会社や社会に対する意識調査」
私見ながら、このデータ。
イマドキの就活生の会社選びの興味・関心をから
求人戦略を示唆する項目がいくつか見えてきました。
折しも、就活シーズン真っ只中。
今回は、このデータから
”就活生への求人戦略(効果的な求人票の書き方など)”を検証してみました。
※資料は、日本能率協会2014年04月17日ニュースリリース資料から引用。


日本能率協会のこの調査のサマリーにもありますが、
つまり、
傾向が伺えます。


この傾向、能率協会のサマリーにもありますが、
傾向が見えます。
また、
・知名度
・給料の高さ
の要素については、意外と占率が低い傾向も窺えます。
上司像からは、
傾向が窺えます。
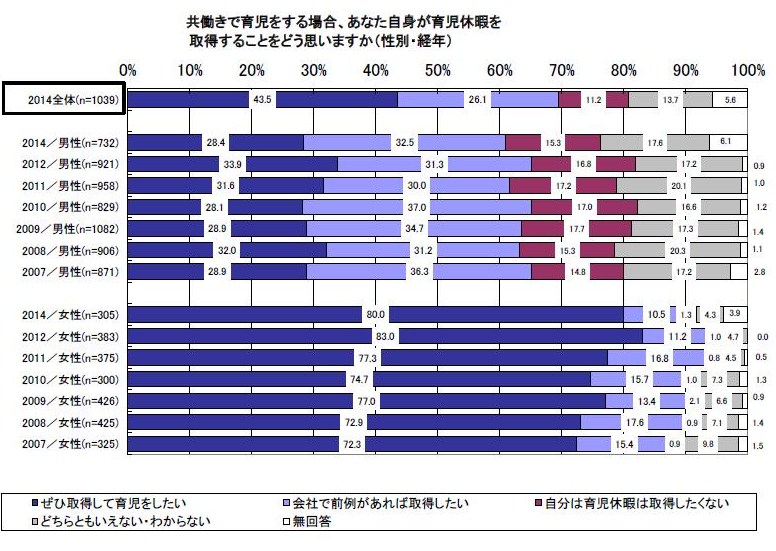
女性の長期キャリア形成指向もさることながら、
この結果は、今後の職場環境の整備の方向性も示唆していると考えます。
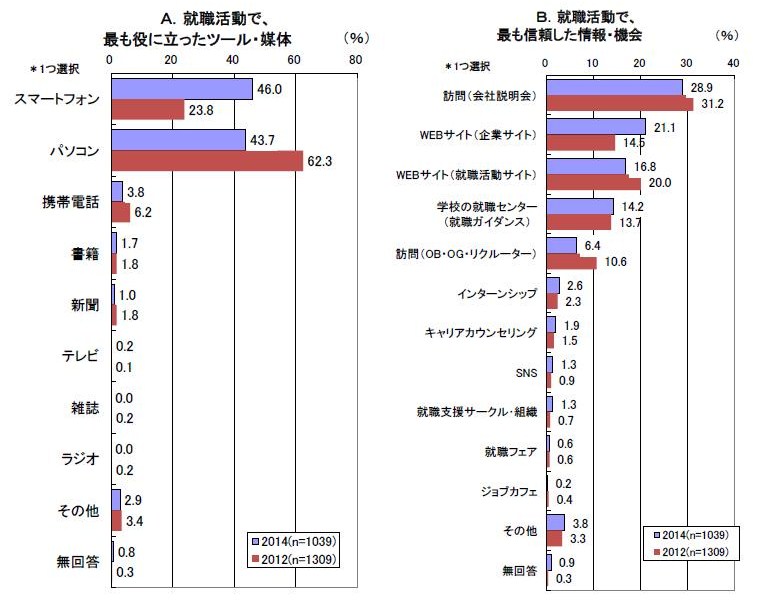
ここで、私見ながら、注目したのは、
の傾向が伺えます。
キャリア形成指向とメリハリのついた人事評価
情報発信の切り口として、例えば、
「会社の雰囲気」 : 50%超
「仕事について丁寧な指導」: 約60%
情報発信の切り口として、例えば、
ここでのポイントは育児休業の取得指向の高さ。
情報発信の切り口として、例えば、
などが考えられます。
就活サイトで情報共有しつつ、実際に会社説明会に出向いて情報収集。
もさることながら、学校の就職センターでの情報への信頼性。
例えば、本コラムで紹介しています
私が実際に求人支援の際にもこちらへの求人をご提案しています。
取材してお伺いした話でもありますが、
ハローワークの担当者毎に学校担当を兼任しています。
つまり、
ということは、
就職センターを訪れる就活生の目に触れるチャンスが
あるということを示唆しています。
求人ルートの一つの選択肢として活用できる媒体と考えます。
また、「会社の雰囲気を重視する」点ついては、
選考プロセスにおいて、
ということを示唆しています。
求人募集をかけてからの
会社説明会・採用面接から、採用担当者として・会社として、
雰囲気をPRする仕掛けも入社モチベーションアップに
有効かとも考えます。
就活生もその周囲にいるみなさんも、広くみれば、
会社のお客様候補ですし、採用というご縁に至らなかったとしても、
「会社を広報(PR)する」視点では、
2014年04月17日ニュースリリース
新入社員「会社や社会に対する意識調査」
調査スペック(回答数1,039人)
・ 2014年3月27日〜4月8日の期間
・ 2014年度入社の新入社員を対象
対象となった新入社員=昨年の就活生。
私見ながら、このデータ。
イマドキの就活生の会社選びの興味・関心をから
求人戦略を示唆する項目がいくつか見えてきました。
折しも、就活シーズン真っ只中。
今回は、このデータから
”就活生への求人戦略(効果的な求人票の書き方など)”を検証してみました。
※資料は、日本能率協会2014年04月17日ニュースリリース資料から引用。
1.独立指向と働き方


・ 定年まで勤めたい :50.7%
※調査を開始した1999年以降、初めて過半数に達したとのことです。
・ 競争をするよりも、ある年代まではみんなで平等に上がっていく年功主義の会社 : 42.9%
実力のある個人が評価され、早い昇進や高い給与が実現できる徹底した実力・成果主義の会社 : 55.1%
日本能率協会のこの調査のサマリーにもありますが、
定年まで勤めたいが、結果に対する評価はきちんとしてほしい。
つまり、
・安定した雇用環境での長期のキャリア形成
・短期に成果に報いる人事評価
傾向が伺えます。
2.会社を選ぶ基準・期待する上司像


この傾向、能率協会のサマリーにもありますが、
当初の会社選びの基準と最終的な選択のギャップ。
「業種」を優先して就職活動を行いつつも、入社の決め手は「雰囲気」。
仕事の内容だけでなく、自分の居場所として心地よい企業を選んでいる。
傾向が見えます。
また、
・知名度
・給料の高さ
の要素については、意外と占率が低い傾向も窺えます。
上司像からは、
「丁寧に指導してほしい」
つまり、仕事を覚える・進める過程での支援を求める
傾向が窺えます。
3.将来のワークライフバランス
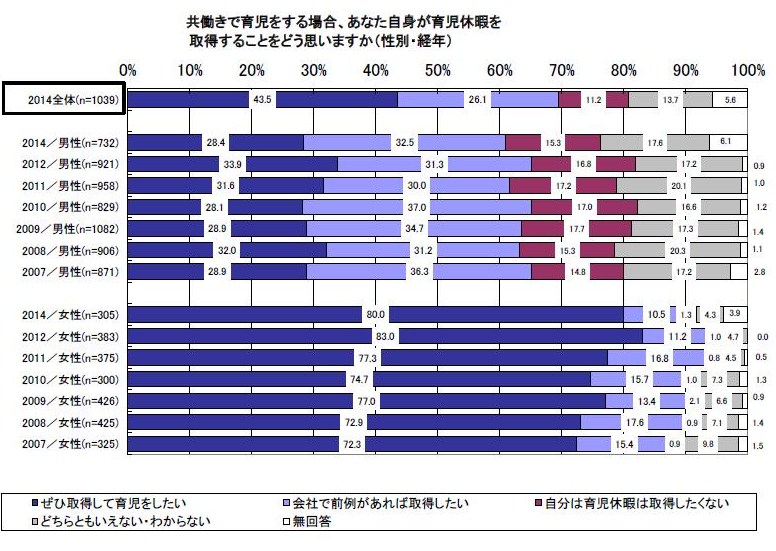
共働きで育児をする場合 女性の回答とのことです。
・ ぜひ育児休暇を取得して育児をしたい : 80.0%
・ 会社で前例があれば取得したい : 10.5%
を合わせると90.5%
女性が育児休業を取得したいと回答する割合は過去最高
女性の長期キャリア形成指向もさることながら、
この結果は、今後の職場環境の整備の方向性も示唆していると考えます。
4.就活の情報収集
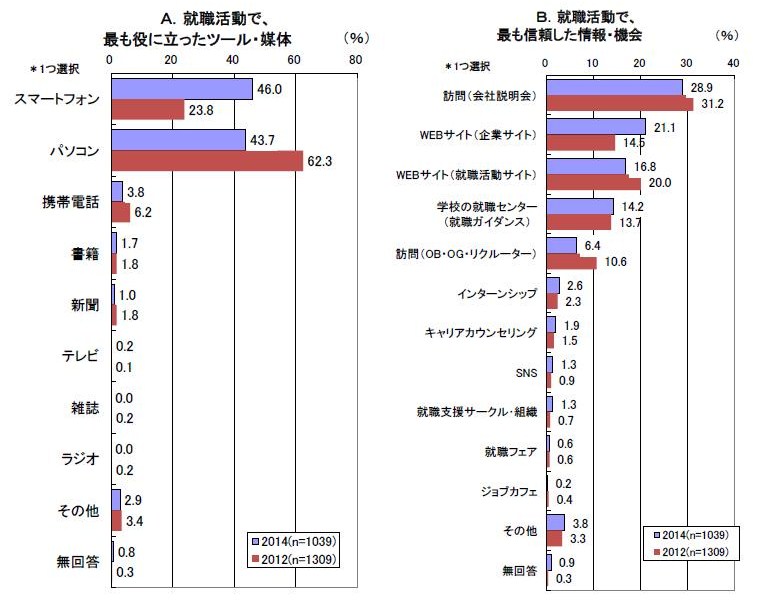
ここで、私見ながら、注目したのは、
・会社説明会
・WEBサイト(企業サイト)
・学校の就職センター
WEBの口コミサイトで企業担当者の応対を情報共有しつつも、
最終的には、客観的第三者(就職センター)からの情報も加味し、
自分の目で取捨選択
の傾向が伺えます。
5.就活生への求人戦略
(1)独立指向と働き方から
キャリア形成指向とメリハリのついた人事評価
情報発信の切り口として、例えば、
・ 3年後・10年後のキャリアパス(会社でどんなポジションにいるか)
・ 将来の期待される役割
・ 人事評価制度の概要
などが考えられます。・ 将来の期待される役割
・ 人事評価制度の概要
(2)会社を選ぶ基準・期待する上司像から
「会社の雰囲気」 : 50%超
「仕事について丁寧な指導」: 約60%
情報発信の切り口として、例えば、
・ 入社後、初期段階での制度だけではない育成・指導体制
・ 職場レベルでの先輩社員の育成・指導での関わり方
・ 仕事の進め方・OJT等の具体的な内容
などが考えられます。・ 職場レベルでの先輩社員の育成・指導での関わり方
・ 仕事の進め方・OJT等の具体的な内容
(3)将来のワークライフバランスから
ここでのポイントは育児休業の取得指向の高さ。
情報発信の切り口として、例えば、
・ 育児休業取得者実績
・ 育児休業等に関する支援体制
・ 育児休業等に関する支援体制
などが考えられます。
(4)就活の情報収集
就活サイトで情報共有しつつ、実際に会社説明会に出向いて情報収集。
もさることながら、学校の就職センターでの情報への信頼性。
例えば、本コラムで紹介しています
新卒応援ハローワーク
私が実際に求人支援の際にもこちらへの求人をご提案しています。
取材してお伺いした話でもありますが、
ハローワークの担当者毎に学校担当を兼任しています。
つまり、
学校との独自のパイプ・情報共有の連携体制がある
ということは、
就職センターを訪れる就活生の目に触れるチャンスが
あるということを示唆しています。
求人ルートの一つの選択肢として活用できる媒体と考えます。
(5)会社説明会・採用面接等でのポイント
また、「会社の雰囲気を重視する」点ついては、
選考プロセスにおいて、
接する社員の雰囲気や誠実さから判断している
ということを示唆しています。
求人募集をかけてからの
会社説明会・採用面接から、採用担当者として・会社として、
雰囲気をPRする仕掛けも入社モチベーションアップに
有効かとも考えます。
就活生もその周囲にいるみなさんも、広くみれば、
会社のお客様候補ですし、採用というご縁に至らなかったとしても、
「会社を広報(PR)する」視点では、
採用担当者も会社のプロモーションの担い手=広報担当
と考える次第です。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
みなさまのご参考になれば幸甚です。
では、また。
※本コラムの内容は、各所取材の上、入手した情報を基に、
記事として掲載させて頂いております。
・新定番!な求人票の書き方のノウハウ・求人戦略情報 満載! コラム好評連載中!
【応募率94.8%! のノウハウ 】: 新定番!な求人票の書き方
▽
http://www.heartrock-noma.com/contentscate_127_1.html
・ソリューション・メニュー
【新定番な求人ノウハウ】94.8%の応募率! 求人原稿コンサルティング
▽
http://www.heartrock-noma.com/contents_327.html
【2時間でわかる!欲しい人材に会社をPR!】”新定番!”な求人票の創り方セミナー
▽
http://www.heartrock-noma.com/contents_297.html
※ご相談・お問い合わせは、下の「ご相談・お問い合わせフォーム」からお願い致します。
【応募率94.8%! のノウハウ 】: 新定番!な求人票の書き方
▽
http://www.heartrock-noma.com/contentscate_127_1.html
・ソリューション・メニュー
【新定番な求人ノウハウ】94.8%の応募率! 求人原稿コンサルティング
▽
http://www.heartrock-noma.com/contents_327.html
【2時間でわかる!欲しい人材に会社をPR!】”新定番!”な求人票の創り方セミナー
▽
http://www.heartrock-noma.com/contents_297.html
※ご相談・お問い合わせは、下の「ご相談・お問い合わせフォーム」からお願い致します。
労務関連ニュース、毎月メルマガでお届けします!